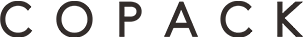ハル(以下H):新作の2019S/Sコレクションのテーマはbloom(開花)ですが、このテーマにした理由はなんですか?
竹島さん(以下T):コレクションを本格的に発表して今回が三回目になるのですが、それ以前のロンドンにいた頃は、コンセプチュアルな表現としての服しかほとんど作った事がなかったんです。リアリティのある服を作り出してからは、クリエイションだけを考えればいいわけではなくて、売れなければ意味がない。そのバランス感覚をつかむのがなかなか難しくて、毎シーズンあちこちから色々言われる反応が怖かったり、思うように結果がでなかったり、どんどん落ち込んでしまって全然楽しめなくなっていました。私はだいたいコンセプトを考えるときに、日常や身の回りのことからインスピレーションを得て、日々感じた事や言葉にならないような自分の思想を服で表現するような感覚があります。着る人や関わる人たちがワクワクしたり楽しい気持ちになるために作っていたのに、私が楽しくなかったらそれは伝えられるわけないですよね。開花に向かうように、ハッピーな気持ちでその道のりを楽しみながら前を向いて歩いていこうという想いを込めて、このテーマにしました。
H:今回の展示では彫刻科の大竹舞人さんと一緒に展示をされていましたが、どういった経緯でコラボレーションの話が決まったのですか?
T:CPKギャラリーでの展示のお話をいただいてから、スカルプチャーと組み合わせたようなインスタレーションをしたいなと考えていたんです。私自身は大竹さんと面識はなかったのですが、ブランドのディレクションなどを手伝ってくれている友人に相談したら大竹さんを紹介してくれました。
H: ayâmeの服と大竹さんの彫刻作品が本当に自然に空間に共存していますよね。会場に入ったとき、吊るされているのが服だと気がつきませんでした。部屋の奥の空間にはセントラル・セント・マーチンズのニット科を卒業されたときのコレクションと大竹さんの作品がこれまたマッチして展示されています。
T: 今まで心のどこかでずっと思い描いていたような展示が実現できたような気がして、とても嬉しかったです。展示会で商業的にアイテムを並べるだけではない新しい魅せ方。設営が終わるまで、どうなるのか未知すぎて不安しかなかったのですが(笑) 私がイギリスでやっていたのは割とアートに寄った表現だったので、またこうして久々に純粋な表現以外何も考えなくていい時間を与えてもらえてしあわせでした。
H: 大竹さんの制作スタイルと共通する部分ってありましたか?
T: 手を動かすことかな。大竹さんは手で布を切り裂いて立体を形成する独自の手法で彫刻を作られるのですが、私の卒業コレクションもタフタにニードルパンチで羊毛をたたいたり※スモッキングをしたり、プリーツ生地にビーズ刺繍をするなど手作業がとても多いんです。手が生み出すものって、有機的で柔らかな要素もありながら内に秘めた強いエネルギーがある気がします。
H: 物としてとてもパワーを持ちますよね。
T:今の時代だからこそ、人の手でつくられる素材や工程をとても大事にしています。どんな人がどんな場所でどのようにつくっているのか、毎シーズン出来るだけ地方のテキスタイル産地に自分で足を運びます。自分の眼で直接確かめてその土地の空気に触れることで、画面越しでは感じ取れない発見が必ずあると思うので。毎シーズン、オリジナルテキスタイルをつくるのですが、今回制作したプリントレース生地は、デジタルではなくシルクスクリーンで何層も色を重ねた上に部分的に樹脂の加工をのせて、フラットな生地でありながらテクスチャーはレイヤーにしています。立体の花柄生地はベルベット工場さんのビロードを使いました。日本には優れたものづくりをしている工場がたくさんあるので、それを活かせるような新しいアイディアや、古い時代から使っているような技術をどうしたらモダンに昇華できるかを常に考えています。職人さんと一緒にものづくりができるのは楽しいですね。

H: デザイナーになられる前は会社員をされていたそうですが、デザイナーの道はいつ頃選ばれたのでしょうか?
T: 私はもともと四年制の大学に通っていたんですが、卒業する頃にデザインがやりたいってやっと気付いたんです。両親に相談したら「やりたいことは自力でなんとかしなさい」と言われて、ひとまず新卒で服飾雑貨の輸入商社に就職しました。ファッション業界には若干その頃から携わっているような感じでした。アパレルのブランドにOEMの時計やアクセサリーを提案する企画営業をしたり、自社ブランドのアクセサリーを取り扱うショールームでプレスアシスタントや卸売営業をしたり、入社したてにも関わらず色んなことをやらせてもらえてよかったのですが、やっぱり私は服を作りたかったんです。ふと10年後にその会社で自分がやりたいことは何か考えたときに、特にないことに気付いて、それなら独立して自分で何かをできるようになりたいと思いました。それからは常に仕事している時、頭の中では未知なる自分のブランド事業に置き換えて妄想しながら仕事をしていました(笑)その会社には結局10ヶ月しかいなかったのですが、その間に日曜日だけ働きながら通えるデザイン学校にも通っていました。そこではパターンとかデザインをひととおり教えてもらうんですけど、技術的なことを叩き込まれるだけで。ここにいても何者にもなれないと思ったんです。
H: それで留学を決意した、ということですね。
T: はい。会社員になってから、何かしたいと思ったときいつでもすぐに動けるためにお給料の大半を貯金していたんです。月に10万円くらいかな。単純計算だけど10ヶ月で100万円貯まるから何かしらできるだろうって(笑)ファッションの世界三大校と言われるNYのパーソンズ美術大学、ベルギーのアントワープ、ロンドンのセントラル・セント・マーチンズの名前だけ知っていて、まずアントワープは言語がわからないので却下。あとは特に調べず、アメリカ=マーケティング寄りのデザイン、イギリス=クリエイティブを深めるという勝手なイメージで、それならクリエイティブを深めたいなと思ったのと、その頃にちょうどリーマンショックの影響でレートが一気に円高になったタイミングが重なったのと、学生ビザでも合法で働けるという情報だけで、イギリスに決めました。10年後思い描いた自分に間に合わせるには今動かなきゃ、みたいな衝動で、年明けの瞬間に特に誰にも相談せず自分の中で一大決心をしました(笑)その時点では年齢のこともあって大学に入り直すことは考えてなかったんです。むしろそれだけは避けたいと思っていました。最初は短期のショートコースだけ受けに行ったのですが、ちょうど卒業コレクションの時期で「お手伝いを探してます」っていうのを掲示板で見かけて。そこでファッション科の日本人のセントマの学生とふれあう機会があり、実際に卒業ショーを見たときに「ああ、私がやりたかったのはこれだ」となったので学部に入る前の「受験準備コース」にアプライしました。とりあえず日本に帰って半年間で、一年分の学費を貯めてイギリスに戻って、その一年間の準備コースでポートフォリオをなどを制作し、やっとBA(学士過程コース)に入り直したという感じです。
H: すごい熱量と決意ですね、、、!!!
T: 何の保証もなく、なんのつてがあるわけでもなく、一寸先は真っ暗闇で、ただがむしゃらに突進している感じでした。会社を辞めて留学することになったときは、親戚が大騒ぎになったり、事あるごとに会社辞めた事を非難されたり、同い年の子たちは立派に社会人をやっていたので日本に帰ってもその歳でまだ学生やってるのという目でみられている気がして、そんな疎外感ですごく肩身が狭かったです。最初は誰も信じてくれないような感じだったので、自分の気持ちは自分で守らなきゃいけない、という感覚でした(笑)その時感じたのが、大人は自分が歩いてきた狭い世界の価値観でしかものをみることができなくて、自分が年をとったら新しい挑戦に飛び出そうとするひとに説得力ある形で大丈夫って言ってあげられる人になろうと思いましたね(笑)留学してからは、誰かに認めてもらいたくて、1つ1つのことに形ある結果を出す事だけにただ必死でした。元々、デザイナーになれる人たちってまた別の世界の人だと思っていたので自分の中で選択肢としてなかったんです。高校生のときから文化服装学院の資料を取り寄せたことはあったのですが、自分がデザインをできるとは思ってなくて。日本での学生の頃は、ダンスやバイオリン、イベントの企画などデザインやファッションとはまったく別のことを色々やっていたんです。その時々で夢中になっていることを突き詰めていたからこそ、ロンドンに来てからは一度も迷うこともなかったです。自分にとって服が一番だということには確信を持っていましたね。なので、年齢だけでみたらスタートは遅いほうですが、私にとってはベストなステップとタイミングだったと思います。
H: 竹島さんのお話を聞いているとあまりにパワフルで圧倒されます。イギリスの他にフランスでも活動をされていましたが、言葉の壁などは感じていましたか?
T: ありましたね。ただ、救いだったのは言葉のプレゼンがなくても引き込むようなビジュアルプレゼンテーションをより評価する環境だったことでした。クリエイションのビジュアルで伝える、言葉ではない私の主張や言わんとする事、そういう言語をきちんとつかんでくれるチューター達がいたので、受け取ってくれている感覚はありました。そういう意味では今の方があんまり伝わらないなあって思うことが多いのかもしれません(笑)
H: 以前このシリーズでkudosのデザイナーの工藤さんにお話を伺ったときも、留学中の大変なエピソードを教えてもらいました。孤独を経験した人ってやっぱり強いなあと思います。
T:私もあまり自分から話しかけたりするタイプではないので、ただひたすら黙々とつくっていました。あと、とにかく自信がなかったので、誰よりも早く来て誰よりも遅くまで学校にいるのを習慣にしていました。朝8時半から22時まで。自信のなさと劣等感はわめいてもどうにもならないので、とにかくやるしかない、徹底的に量をこなして気を紛らわすしかないみたいな(笑)現地での生活費は全部自分でやりくりしていて、学校にいる以外の時間はほぼアルバイトに費やしていたので、飲みに行くのも稀でした(笑)でも辛いと思った事は全然なくて、日本で会社員を続けていることを想像したら、やりたいことを思い切り突き詰める時間は本当に贅沢で、すごくしあわせでした。いま思い出しても人生の宝物の時間です。もともとニット科に入ったのですが、いわゆる伝統的なニットではなくて、新しい素材と組み合わせたアイディアに挑戦して、今まで見た事ないような独自の編み地を作りましょう、というスタンスで、とにかく自由でした。私は刺繍と組み合わせたり、異素材をレイヤーにして熱加工をしたり、編み機だけでは生み出せない新しいテクスチャーをずっと探求していました。活動を見てくれている人って意外といるんですよね。学校の中には、チューターに気に入られるために仲良くするのが上手な子とか人脈づくりに抜け目がない人とか色々いるんですけど、そういう策略的な人間関係の構築ができないので、基本一人でいたんですが、知り合いは全然多くなくても不思議とキーパーソンとなる人と繋がって。作品に興味をもってくれた人が向こうからコンタクトをとってくれて繋がって、またそこから人間関係がどんどん広がっていったり。必要なタイミングで必ずいい出会いがありました。ありがたいことに、今もその頃も、出会いの運だけはすごくいいです。

H:ファッション業界に入ってみて疑問とか気付いたことはありましたか?
T: 私が会社員だった頃は営業部配属だったのもあり、いかにスピード感をもって効率よくお金を稼ぐかが大事な世界で、むしろ会社はそれ以外考えてなくて正直自分には向いていないと思いました。でも、ビジネスのみで考えたらその感覚も必要なんだろうなとは思うので、あれはいい経験でしたね。ときには売らないといけないというプレッシャーに押しつぶされそうになることがありますが、、、(笑)あとは日本のファッション業界の空気って、自分の感覚ではなくて他者からの情報でブランドやデザイナーを判断している風潮があるなと思います。例えば、海外のどこの誰がこう言ってるから、どこのお店に置いてあるから、とか。ロンドンにいるときはたとえデザイナーが無名であったとしても分け隔てなくいいものはいいと評価してくれる文化だったので、そういうところは違うなあと感じますね。

H: 日本は若手が育ちにくい環境だと私も感じています。もっとみんなにとって心地のいいシステムを自分たちでつくっていきたいですよね。
制作する上で一貫したテーマはあったりしますか?
T: 2年前に制作した卒業コレクションでは私の祖母がつくった一着の服をインスピレーション源にしています。私の家では祖母がつくった水色の子供服のドレスが代々受け継がれているんです。叔母から母へ、母から私、そして妹へ。旅をするように何十年に渡って着られてきたその服がみてきた景色、辿ってきたストーリーを想像したことが始まりでした。そして女性名詞、男性名詞があるように、ドレスを主人公としてみたとき、そのドレス自体はとてもフェミニンなアイテムだけど、もしかしたら本当は男の子かもしれないんじゃないか?と思って。既成概念にとらわれずに普段とは違う視点で服を見れないかと考えたんです。フェミニン、ガーリー、可愛いというのはドレスを見る人側の既成概念であって、ドレスそのもののパーソナリティーはきっと、ひとにどう思われたいかで着飾っているのではなく、ただ生まれ持った要素をありのままに持っているだけ。そのようなストーリーから、本来デコラティブとされる装飾的な要素を用いながらも、削ぎ落とされたミニマルに落とし込むことを目指しました。自分が生まれ育った環境の手づくりに囲まれたぬくもりの記憶と、パリでのクチュール現場の経験、そしてまだ見ぬ自由であたらしいクリエイションをまっすぐに評価してくれるロンドンという環境、自分がそれまで歩んできたすべてが組み合わさったからこそ作れた服でしたね。余談ですが、2年前に日本に帰国してからすぐ、この卒業コレクションの原点となった祖母の家で、祖父の油絵のアトリエだった部屋を2ヶ月かけて自分たちでリフォームして、アトリエをつくったところから、アヤームの活動が始まりました。なので、このコレクションはそんな意味でもストーリーのはじまりのような感じです。フェミニンなのかマスキュリンなのかどっちなの?と聞かれることも多いんですけど、そんなにカテゴライズする必要はないと思っていて。その人が受け取ったように着てもらえればそれでいいです。日本人って特にカテゴライズしたがるなあ、と思うことが多くて。その枠にはめられないぞ!っていう気持ちは常にありますね(笑)「こういう見方もありますよ」、っていうことをふわっとコレクションを通して伝えられたらいいなと思っています。物の受け取りかたは自由であってほしいです。がつんと他人に価値観を押し付けるわけでもなく、異なる価値観を排除しようとするわけでもなく、ふわっと越える姿勢、その柔らかさの中に本当の強さと自由があると思います。自分と異なる人たちを敵視したり否定するわけではなく、あなたはあなた、わたしはわたし、お互い幸せに生きましょう、という調和と共存を目指すスタンスです(笑)
H: そういう気持ちって今の時代すごく必要になっている気がします。対立するだけじゃない、明るくて柔軟な強さ。


T: 私の中で大事だなと思うのが、いかに日々わくわくする時間とか楽しい気持ちになる時間を人生の中に増やせるかなんです。服を通してそういう気持ちになるのって一瞬かもしれないけど、そういう力になるような、纏う人がちょっと特別な気持ちになるようなものがつくれたらいいなと思っています。多種多様に溢れた他人の価値観に左右されて生きるよりも、全員には理解されないことを恐れず、弱さも迷いも受け入れながら、ありのままの自分を肯定して、自分らしく生きることを模索し続ける人の背中を押せるような服だったらいいなと思います。アヤームのコンセプトは「ニュークラフトマンシップ」と「今日を誇れる服」なんですが、自分が自分らしくいればきっとその日を誇ることができると思うんです。そして、その心の余裕からは、その人自身がもつナチュラルな色気が引き出されると思います。過去でも未来でもなく、いまこの瞬間をのびのびとしなやかに生きるための自由な服。ayâmeアヤームの由来の、âme「 アーム」の語源はフランス語の「魂」なんですが、「アヤーム」という音としては「アイアム」にも聞こえるように、その人がその人であることをそっと背中を押す服でありたいですね。
※スモッキング:布に細かくひだをとり、ひだ山を刺繍(ししゅう)糸で模様をつくりながらとめていく手芸。スモック。(デジタル大辞泉の解説)
【編集後記】
また一人、ものすごいパワーを持った女性に出会ってしまいました。最近よくSNSなどで「どうしたら○○になれますか?」という質問を見かける。
○○に当てはまる言葉は様々で、具体的な職業からどうしたら有名になれるか?など。そんな質問を他人に気軽にしちゃう人はぜひとにかく竹島さんの「手を動かすこと」を参考にしていただきたいと思います。何者かになるにはどんなときも自分に正直に、考えることを止めず、手を動かし続けるしかない!ですね。話は変わりますが、卒業コレクションの写真の中に友人の男の子を発見。カーネーションのような、貝のひだのような装飾が施されたピンク色のセットアップにおそろいの帽子も被っている。しっとり甘い雰囲気を持っている彼にこの服が絶妙にマッチしていて、ayâmeは男の人も着るっていう意味がわかる。うっとり。その人がayâmeを選びさえすれば、きっと服はもうその人の一部になれるんだろうな。
そんな人間になりたい、とayâmeの服にほんのり憧れを抱くおハルなのでした。
【ハルマリPROFILE】

haru.
同世代のメンバー4人を中心に制作されるインディペンデントマガジン『HIGH(er)magazine』の編集長を務める。『HIGH(er)magazine』は「私たち若者の日常の延長線上にある個人レベルの問題」に焦点を当て、「同世代の人と一緒に考える場を作ること」をコンセプトに毎回のテーマを設定している。そのテーマに個人個人がファッション、アート、写真、映画、音楽などの様々な角度から切り込んでいる。https://www.instagram.com/hahaharu777

小林真梨子
1993年、東京生まれ。大学入学をきっかけに写真を始め、「楽しいこと」を追求しながら写真を撮っている。月刊誌『MLK』を制作ほか、アパレルブランド等の撮影も行う。instagram.com/marinko5589
presented by CPK GALLERY

「服の見せ方」を考えるギャラリー
https://www.instagram.com/cpk_gallery
次回展示案内

展示概要
HANGER HOLIC展 「HOOK UP」
■会期:
11月22日(木) ~ 12 月14 日(金)13:00-18:00
※日曜休廊(祝日23日は開廊)
11 月22日(木)18:00~ レセプションがございます。どなたでも、ご来場頂けますのでお気軽にお越しください。